【新人MR向け】認定試験のオススメ勉強方法4選

テキストのボリュームが多すぎて勉強がはかどらない!
という新人MRの皆さん。勉強方法少し変えてみませんか?
今日は認定試験の勉強方法について
・勉強しているつもりなのに模試の点数が上がらない
・いつも同じ問題で間違えてしまう
こんな悩みがある人、なんとなくテキストを読んで勉強した気になってるのでは?
「目的意識をもってテキストを読むと記憶に定着しやすい」
という部分で書いていきます。
認定試験勉強法について。テキスト3冊持ち歩いてるのを見ると大変だな…と思います。https://t.co/NjeKsdpBdl
— ケースケ@mr-lifehack (@Keisukemrlifeh1) October 10, 2018
※勉強するための時間確保に関する記事はこちら
具体的には4つに分けて解説します。
- 答えはすべてテキストの中に
- 問題集は弱点を見つけるツール
- 色々手を出しすぎない
- 人にプレゼンしてみる。口頭試問のススメ
時間が無い人は2つ目だけでも読んでみてください!
答えは全てテキストの中に
✔︎だらだら読んで本当に頭に入っているのかな?
単なる流し読みは記憶には定着しないですね。
ましてや疲れている仕事終わりなんかに読んでも眠くなるのがいいとこです。
以下のサイトにこんな文章があります。僕もこれには同意します。
絵本など圧倒的に文字が少ない本であっても、書かれている内容を一時一句覚えることはできません。ましてや教科書は小説と違って自分の感情が揺さぶられにくいため、なおさら記憶に残りにくいはず。つまり教科書の内容をすべて覚えるのは人間の限界を超えていることなのです。
MANA-BU(マナ部) 教科書や参考書の内容をサクサク覚えるための裏ワザ
https://fujimotokenko.org/kyoukasyo-1go1kuyondemo-hayakukioku.html
認定試験の問題、回答は支給されたテキストの中からすべて出ます。
ではテキストを読み込んだらいいのですが、
上記サイトには7回読め!というなかなか厳しい現実が書かれています。
MR認定試験の問題って結構細かい用語の正誤問題などあるので、
問題文を見ると合っているように見えたりするんですよね。
ではどうテキストを読んでいくか?支給された問題集を活用しましょう。
問題集は弱点を見つけるツール
✔︎問題文そのものに価値がある。問題集こそボロボロに。
会社から一冊は問題集支給されたと思います。
(もし支給されていない場合は、Amazonでも買えるので購入しましょう!)
問題集は、テキストを読み込むきっかけに使うツールだと思ってください。
実例を見ていきましょう。
問. 細胞質のグルコース分解反応は解糖系と呼ばれ、これによりピルビン酸とATPが生成される。
答え:正
そんなに難しい問題ではないですね。
答え合わせして、「あ、正であってた。はい次の問題…」となりがちですが、
この問題の単語を全て説明できるでしょうか?
細胞質?グルコース?解糖系?ピルビン酸って何をするの?ATPって何…?
テキストに索引がありますよね。多くの単語はここから逆引きできます。
説明できない単語はこの索引から引き直して読み込みましょう。
このように興味を持った状態でテキストを読むと記憶に定着しやすいです。
参考サイト 2章に詳しく書かれていました。
STUDY HACKER:脳の特性を活用せよ! 京大生が教える『科学的な復習方法』4選
https://studyhacker.net/columns/kagakuteki-hukushu-method
この作業を怠ると、「上記の問いに対する答えは正」と丸暗記して、
ちょっと単語が変わると「あれなんだっけ?」となります。
例えば、
問1:細胞質の~、これによりマレイン酸とATPが生成される
問2:細胞質の~、これによりピルビン酸とADPが生成される
こんな感じで単語が変わると、本当に理解していないと「正!」とやりがちです。
(実際にはこんな問題出ないと思いますが…)
同じ問題集を繰り返すと問題文を覚えるので、反射的に正誤問題はわかってしまうんですよね。
3択、5択も同じです。問題集は複数回やっていい点とれるのに、模試だと全然…
という人は、このパターンに陥っている人が多いです。
3択、5択問題も同様に、問題分と回答部分の単語に説明ができないものがあれば、
ひたすらに索引から単語を逆引きして読み込んでいく。
そうすると一回分の問題集でも、結構なページ数のテキストを読むことになります。

色々手を出しすぎない
✔︎会社から支給される問題集だけでOK
では初見の問題にたくさん触れたらいいのでは?と思う人へ。
今支給された問題集だけで充分です。
その問題集に書いてある単語がすべて説明できれば、まず間違いなく認定試験は通ります。
およそ7割の人が通る試験です。満点を取る必要はないので、
とにかく支給された問題集がボロボロになるまで活用して、テキストを読み進めていきましょう。
会社によっては外部業者のセミナーも受けられる会社があるみたいですね。
無料なら受けてみても良いかもしれませんが、自分でお金払って聞きに行くぐらいなら、
問題集→テキストの読み込みをひたすら続けた方が確実ですよ。
わからない単語を一つずつつぶしていった方が早道です。
人にプレゼンしてみる。口頭試問のススメ
✔︎同期、先輩を「生徒」だと思ってプレゼンしてみよう
単語が説明できるか?のジャッジは、人に話して伝わるかが一つの基準です。
同期が近くにいる環境の場合、同期同士で問題を出し合って、
「口頭で答える口頭試問」が効果あると思います。
5感を使うと記憶に定着しやすいと言われていて、
教科書を読むときに音読で読むと効果が高いともされています。
さらに人に教えるという行為は、頭の中でまとめて、
アウトプットするという行為なので、脳を大きく刺激するらしいです。
参考図書
✔︎自社製品のパンフレットの単語は完璧?
今すでにMR活動をしているという人。
添付文書をはじめ、パンフレットに書かれている単語は説明できますか?
わからなくても大丈夫です。その単語がMRテキストに載っていれば、索引から引いて確認してみましょう。
(もし載っていなければ他の方法で調べてくださいね!)
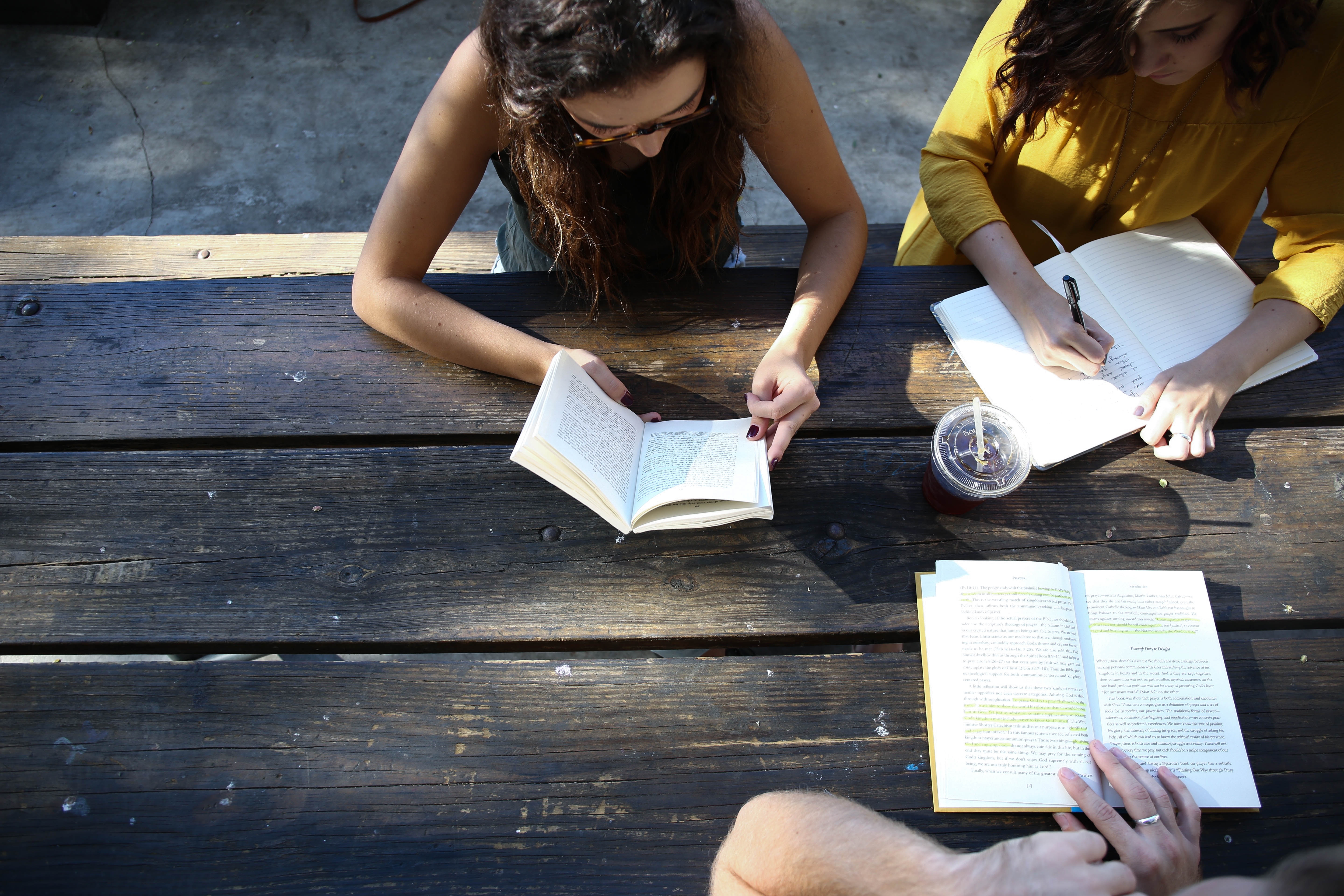
まとめ
ダラダラ読みから、目的意識をもって読み込むように変えていきましょう。
認定試験以外の勉強でも役に立つはずです。
例えば文献を読んでいて、自分の知らない報告やデータが記載されていた場合、
丁寧にリファレンスが記載されていることが多いです。
そのリファレンスを読むと、詳しいデータに関する情報が取れるのです。
勉強も仕事の一貫ということで、勉強してサクッと合格しましょう!
-
前の記事

【新人MR向け】認定試験の勉強っていつすればいいの? 2018.10.09
-
次の記事

【オンコロジー新薬】XPO1阻害剤selinexorとは? 2018.10.11








コメントを書く